
子どもたちの日常に探求のきっかけを
教材開発チーム
私はもともと勉強が得意なタイプではなかったのですが、化学や生物は好きでした。そして“学ぶ楽しさ”を実感したのは大学での研究です。正解のない課題に向き合って、自分なりに答えを探していくことに“ただ知識を覚える”とは違った面白さを感じました。そして自分で考え、調べ、試行錯誤する、そうした“探求する面白さ” を多くの子どもたちにも伝えたいと思うようになりました。
ラインズを選んだのは、まさにその思いと重なったからです。基礎学力の定着を大切にしながら、勉強が苦手な子どもたちにも「学ぶって楽しい」と思ってもらえる教材づくりに取り組んでいる点に強く共感しました。私自身が感じた学びの面白さを、今度は誰かに届けたい、そんな思いで入社を決めました。
入社1年目は、子どもがどの教科書を使っていても解けるドリル問題をめざし、小学校理科の問題を調査しました。たとえば、ある教科書では植物の育ち方をヘチマで学び、別の教科書ではツルレイシで学びます。そのため、題材によっては一部の子どもにとって問題が解きにくくなることがあるのです。
また、年次が上がるにつれて「理科という教科で、本当に伝えるべきことは何か?」という本質的な部分に目を向けるようになりました。今は、理科教育全体を俯瞰(ふかん)しながら、子どもたちがどんな流れで学ぶのが効果的かを考え、それを教材としてかたちにすることに日々奮闘しています。
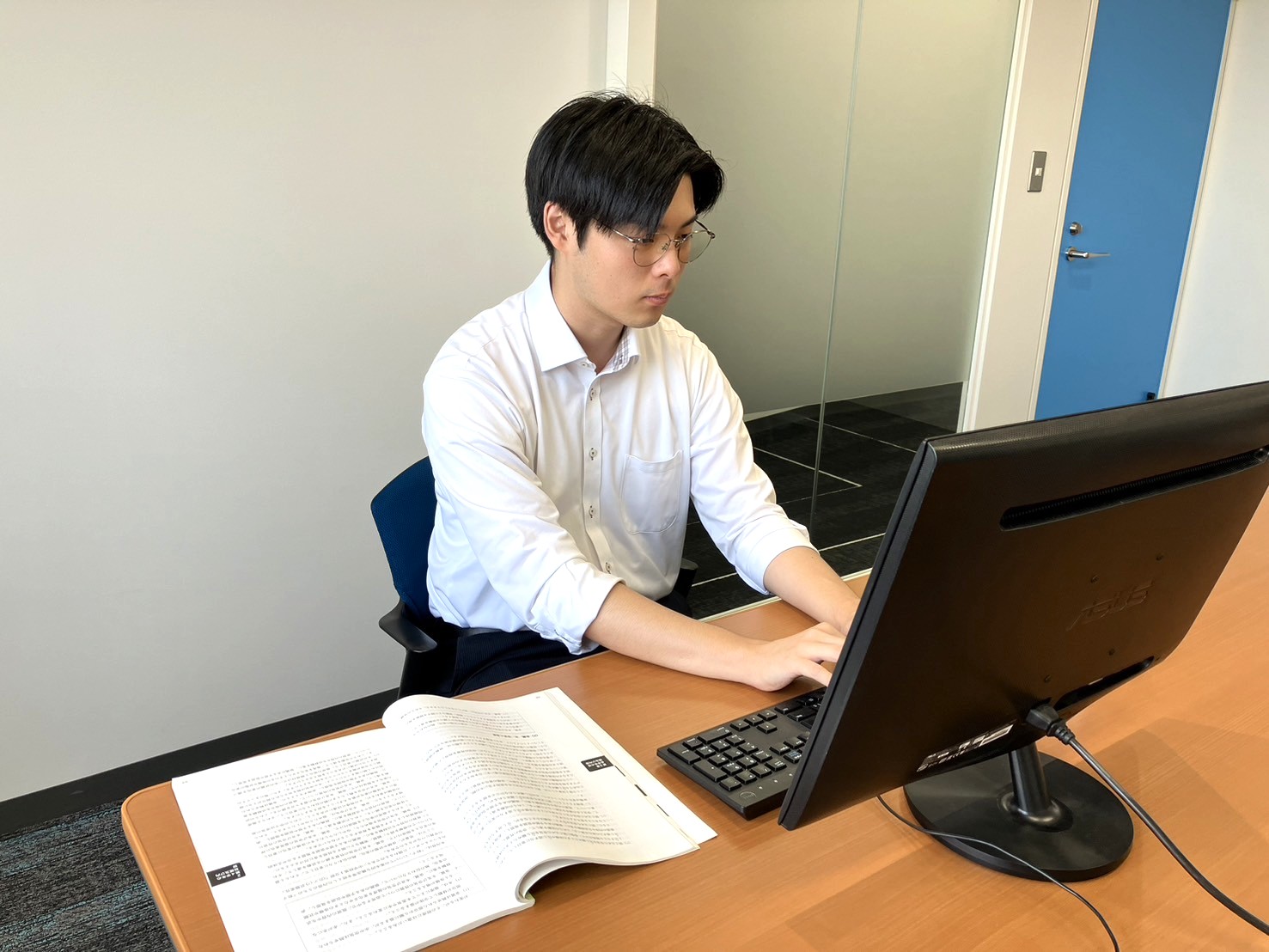
実際に、ラインズのサービスが使われている授業を見に行ったことがあります。それまでは「本当に子どもたちが解きたいと思える問題をつくれているのだろうか」と不安に思うこともありました。でも、子どもたちが何の違和感もなく教材をひらき、自然に学び始めている姿を見たとき、「自分の作った教材が日常の中に“あたりまえ”として根づいているんだ」と実感できて、ほっとしました。
そして同時に「勉強が苦手な子どもでも、学びに向かえるような教材をつくりたい」という、もともと自分が目指していたことがしっかりとかたちになっているのかなと感じることができました。
ゼロから教材を生み出していくことは大変ですが、その分、完成した問題がそのままサービスに反映され、実際に子どもたちに使ってもらえているという実感が持てるのは、大きなやりがいです。
これまでで一番大変だった業務は、入社2年目の時に社内のワーキンググループ※でリーダーを任されたことです。課題は、教材内の「ふりかえり機能」を子どもたちや先生方にとって、より使いやすくするための改善案をまとめること。右も左もわからないままのスタートで、自分の力不足を痛感する日々でした。
特に苦労したのは、見通しを立てることです。「いつまでに何を決める必要があって、そのために何をすべきか」という計画がなかなか立てられず、立てたとしても経験が浅いために自信が持てない。さらに、目標設定があいまいだったことで、ミーティングを重ねても結論が出ず、時間だけが過ぎていくということも…最初に想定した期日通りにはほとんど進まなかったですね。
そんな中で学んだのが“メンバーに頼る”ことです。チームを2つの班に分け、役割を明確にした上で、私は両方に携わりながら全体を進行しました。最初は目標設定からミーティングの進行、意思決定まで全て自分でやらなければ、という思いが強かったのですが、役割分担をすることでより効果的に業務を進めることができ、なんとか最後は社長に提出する提案書をまとめ上げることができました。ワーキンググループは慣れない業務も多く非常に大変でしたが、結果的に一人で抱え込まずに他者に頼ることの大切さを実感でき、自分にとって大きな経験になったと感じています。そして何より、このワーキンググループを完遂できたのはメンバーのおかげなので、一緒に奮闘したメンバーには心から感謝しています。
※ワーキンググループ=特定の業務や調査をするために作られた部会

これからも理科担当として、知識を深め続け、それを教材に反映させていきたいと思っています。ただ正しい情報を届けるのではなく、「理科って面白い」と思ってもらえるような教材をつくりたいです。理科が苦手な子でも、「なんだかちょっと気になる」「これは面白いかも」と感じてもらえるきっかけをつくりたいと考えています。そしてゆくゆくは、答えのない問いに向き合って、自分なりに考え抜く、そんな“研究者的な視点”を持つ子どもが一人でも増えたら嬉しいです。すべての子どもたちが研究者のように、未知の課題にも興味を持って立ち向かえるような、そんな学びに向かう土台を育む教材をつくっていきたいです。
こちらから







